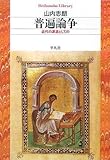[補足あり]
- 作者: ピーターバーク,Peter Burke,井山弘幸,城戸淳
- 出版社/メーカー: 新曜社
- 発売日: 2004/08
- メディア: 単行本
- 購入: 6人 クリック: 40回
- この商品を含むブログ (31件) を見る
ピーター・バーク『知識の社会史』は、「文化史とは何か?」がこの分野のよくできた概説書なのと同じく社会科学で流行の知識人論を概説しているかのような構成で、「近代前期16〜18世紀のヨーロッパに時代と空間を限定して、知識人の歴史を記述した」という冒頭の断り書きの意図が、ざっと一読しただけではよくわからなくて、
いちおう著者は、本書をまとめたのは、このテーマ(知識人)にこの視点(時空を近世に限定した歴史学)からアプローチする研究がエアポケットのように何故かこれまでなされていないことに気付いたからだ、と言うのですが、
ゆっくり読み直してみると、どうやら著者は、華麗な知識人論の数々が歴史学の視点から見て色々「怪しい」と思っている気配がある。正面切って批判したり、「作られた知識人神話」を解体するのも野暮ったいので、さらっと書いた、ということのようですね。
たとえば「schoolの語源は暇です」と色々な人が言うわけですが……、
「スコラ(schoolの語源)の人」(ほぼ「暇人」の意味だと思う)というのは、人文主義者・ユマニストの考え方を取り入れた新しいカリキュラムを大学に導入した人たちが、教会の伝統的な学識・学芸をバカにして言った言葉らしい。
イタリア発祥のユマニストは、都市で塾を開いたり、有力者の家庭教師をする新しいライフスタイルの人たちだったわけですが、彼らが教会の学識・学芸を「暇人」と呼び得たのは、こちとら神に奉仕するのではなくて、ちょうど大道芸人が身体芸で暮らすように、頭脳芸で生きているんだ、という感慨だったのかなあと思います。
ピーター・バークは、(少なくとも一部の)ユマニストにとって「教えることは職業というより宿命であった」と言いますが、たいして儲からないけど、オレにはこれしかない、という芸人っぽい生き様を言っているんだろうと思います。
大学はスキルの習得・訓練の場でなく、教養・学びの場なのです、と言いたい「人文学」の先生が、「Schoolの語源は、暇、ということなんやで」と言うのは、なんだか話がねじれてしまっていることになりそうです。
人文主義は、絶対・普遍の神に仕える生き方を「暇人」と言い放つ俗世の人生から出てきた知恵のはずだったんですけどねえ……。
ルーセンシオが学生を装って商家へ潜り込もうとするところを見て、イタリアのユマニストというのはこういう都市に浮遊するチャラい連中だったんだろうなあ、と思う。
- 出版社/メーカー: ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
- 発売日: 2010/10/27
- メディア: DVD
- クリック: 6回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
大学のベースに人文的素養を置いたほうが上手くいく、という議論は、ドイツのメランコリックな哲学を学べ、ということではなく、イタリアの伊達男の処世術をまず身につけろ、話はそれからだ、ということだったのかもしれませんね。人文主義とは、ぐうたらな「暇人」を夢想することではなく、如才ないマメ男のススメなのでしょう。
そして一方、大学院へ進学して朝から晩までゲームやってCD聴いて、あとは分析哲学のトレーニングとして中世教会の論争を解読する、というのは、正しく「暇人/スコラの人」だし、そうやって、北米文化という絶対・普遍へ仕える人になっていくのだろうと思います(笑)。
- 作者: 山内志朗
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2008/01
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 102回
- この商品を含むブログ (50件) を見る
-
-
- -
-
とはいえ、このような物言いに対しては、「語源など気にせず、とりあえず、相手に一瞬であれ、へえ、なるほど、すげー、と思わせればいいんだ、保身だろうとなんだろうと、そのような臨機応変こそが渡世の習いだ」という下流社会(乱世?)を生き抜く勝ち組狙い(笑)な反論もありえないことではなさそうで、実際、「大学人」は「自由」という浮力を得るための前提であった教会のドグマが弱体化した近世に入って、独自の仰々しい服装・風習で、自らを特別な集団として自立的に演出していったようです。これがいわゆる「学問の自治」。
(その結果、ゲーテがライプチヒ大学で教授の権威に感銘を受ける、というようなことにもなったらしい。)
で、「大学人」の権威を強調するときには、今度は「アカデミック」という言葉が使われたりしまして、これはもともとプラトンの学園の名前で、ルネサンスの文芸復興でイタリアの貴族たちがパトロンになって乱立した知識人サロンがプラトンにちなんでアカデミーと呼ばれ、自然科学の時代である17世紀には絶対君主の王立アカデミーなどが作られて、これが今日の学会の原型になった、とされるようです。
大学の先生たちは、しばしばボケたことを言うのだけれども、それでもなれなれしくツッコミを入れたりすることがはばかられるのは、そういった、ほとんど神話的な「アカデミシャン」のオーラがあるからだと思います。知の神殿の司祭、ですね。
でも、皆様もはやご存じのごとく、今は、「神話」のあるところに必ず「つくられた説」が発生するのが世の習いとなっております(笑)。
わたしたちは、そのような思考法を、他でもなく「アカデミシャン」から教わりました! これは、恩返しの絶好の機会なのかもしれません!
だいいち、古代ギリシャのプラトンとルネサンス・文芸復興とニュートン、ライプニッツの自然科学だなんて、話が飛び石状態になっており、いかにも、いいとこ取りの「偉人伝的歴史観」の典型に見えてしまいます。
古代から連綿と続く「アカデミー」の歴史というのは、たぶん、ない。
王室や貴族や有力者が出資して、知識人を雇うことで近代初期の「アカデミー」が成立したそうですが、この形は、オーケストラの誕生とちょっと似ているようにも思われます。今で言えば政府系シンクタンクですね。
ウィーンやベルリンが、音楽協会を結成し、常設オーケストラを持つことで「音楽の国」を事後的に演出し、神話化したように、アカデミーの権威は、ウェストファリア体制で領土の境界がひとまず確定したヨーロッパの領主たちが、平時の「知性の国」を演出する仕掛けだったんでしょう。
-
-
- -
-
以上、ピーター・バーク先生の本のごく一部、第2章だけの話ですけれど、近代初期に聖職者、大学人、文筆家、書記・官吏、司書、ジャーナリスト……と、今日につづく知識で生活する職業形態がひととおり出揃ったのを横並びで読むと、ああ、こういう感じだったのか、と色々想像が広がります。
まともに書けば十分一冊の書物を必要とするテーマである、近代初期の〈知識人〉[原文は clerisy らしい、聖職者 clergy に対応する世俗の階級を指す言葉らしいので、水村美苗風に「叡知の人」とするなど、引っかかりのある訳語を当てたほうが読みやすい気もする]についてこれまで簡単に論じてきたが、少なくとも〈知識人〉が仕事を求めた多種多様な制度を考慮に入れなければ、彼らのアイデンティティを定義することが困難であることは分かっただろう。つぎの章では、〈知識人〉の活躍の場となった制度や知識に対するその寄与を調べることにしよう。(訳書、55頁)
[補足]
第2章に入ると、近世の「大学」と「アカデミー」の関係がもう少し詳しく説明されますが、これは相当ややこしそうですね。
旧態然とした「大学」に対して、「アカデミー」はユマニスト系の人たちの自然科学に代表されるような新しい学問の場になって、絶対君主のような新興勢力もこっちに付いた(「大学」は聖職者という国王への「抵抗勢力」の巣窟のようなところもあるし)、という物語にするのがシンプルでわかりやすいのだけれども、当時の「大学」が実際に何を教えていたのか、わからないことも多く、古くさいだけだったわけでもなさそうで、しかも、「大学人」が同時に「アカデミー会員」であることもあったみたいです。
ただし少なくとも、「アカデミー」がプラトンに由来する古い名前を冠しているけれども制度としては「大学」より新しくて、近世には、新興の制度であることの利点を活かした機動力があり、社会的に訴求力のある活動ができたように見えますね。(そして18世紀には、「アカデミー」とか「コレギウム」といった名前の様々な分野の専門知識の教育機関が登場するそうです。)
いつのまにか「大学人」が自分たちを「アカデミック/アカデミシャン」と呼ぶようになったのは、ヌケヌケと新参者たちの手柄、「アカデミー」が獲得した権威や成果を自分たちのものにしてしまっているように私には見えます。(19世紀に特にドイツで大学が再編されて再生し、他の教育機関を圧倒するようになるのも大きいようですが。)
戦後の日本は、高等教育・研究機関を全部「大学」という名前にして、「学会」は大学教員の親睦団体もしくは互助組合みたいになっている大学帝国主義な環境なので(しかも他国のアカデミーやその他の教育機関の名称も日本語では「大学」(そして研究オンリーの機関はすべて「○○研究所」)という訳語を当てる慣行が長くつづいた)、世の中には知識を取り扱うもっと別の制度や可能性が色々あるのだということを忘れないためにも、教会の「暇人」な聖職者の「スクール」と、都市生活者の頭脳芸・処世術としての人文学と、国王のお墨付きを得た専門家集団アカデミー(情報交換だけでなく知識・技能の教育・伝承もするようになる)……等々はそれぞれ別物で、今はたまたま、全部ごっちゃに同じ場所で同じ人が兼ねることになっているのだ、と思っておいたほうがよさそうですね。(前にも同じようなことを書いたような気がしますけれど。)
参考:吉見俊哉の大学論は、わかりやすいようでいて、予定調和的に現状を肯定しすぎかも。http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20110825/p1

![じゃじゃ馬ならし [DVD] じゃじゃ馬ならし [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AlXX092PL._SL160_.jpg)