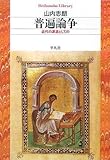「普遍」の話をしようと思うとこれ、ということになるのでしょうか。
- 作者: 山内志朗
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2008/01
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 102回
- この商品を含むブログ (50件) を見る
いつものように、入り口の手前で読むときの構えをあれこれ考えているに過ぎないが、
実は初出単行本(1992年、哲学書房)の帯には
「いわゆる「普遍論争」は十九世紀に捏造された」
と謳われていたらしい。カルスタ・ポスコロの「近代によって創られた説」の嵐が吹き荒れていた時代のなかで書かれたということになりそうだ。
そしてわかりにくいと評判の「馬の馬性」の話などが出てくる最初の章の補足的な説明を読んで、ああそうか、と思った。
中世の終わりになると、論理学は大学で形而上学と別立てで教えられるようになったという記述があり、別のところに、最近では、中世哲学について、「声」の問題を考え合わせたほうがいいと言われ始めている、という補足説明がある。
どうやら中世の論理学は、現代数学が命題の漏れのない証明を要求されるような意味での自給自足の体系ではなく、比喩的に言えば、普遍者(その最上位としての神)が語られることになるのであろう形而上学に向けて天井(天上)が開いており、もう一方で、証明というより説得の技術として弁論・説教に利用されるという意味では、市井に向けて、床が抜けているらしい。
「見えるもの/見えないもの」という補助線を著者は導入しているけれど、論理学は顕教(弁論・説教)と秘教(形而上学)の媒介者・中間者として、記号を取り扱う術策であった、と考えておけばよさそうだ。
-
-
- -
-
- 作者: エトムント・フッサール,立松弘孝,松井良和
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1970/05/07
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
かつて論理学は上と下をつなぐ中間・媒介だったのに、フッサール様は論理学研究から「厳密な学としての現象学」を構成してしまうのだから、論理学は20世紀に入って大いに出世したのだなあと半ば呆れる。
論理学からめでたく現象学の人に変貌すると、直観の「生き生きした現前」を説明するときに音楽の例を出したりするので、「生き生きした現前」という言葉遣いもあって、
現象学とはあらゆる前提を還元した直観に遊ぶ仙人の境地
みたいな気がしてしまうのだけれど、どうやらそういうことでもないらしい。
提唱者の目論見によると、直観の「生き生きした現前」を適切に分析することで、いわば世界の内と外が反転して森羅万象を厳密に説明できるはずなんですよね、たぶん。
で、そういう現象学さんの説明を読んでいると、なんだか、パソコンの自己診断プログラムのような気がしてきた。
意識が意識を分析するのって、コンピュータが自らのアプリケーションとして自力で自分自身を診断するのに似てますよね。マカフィーやシマンテックだ。
で、知覚や認知を考察したい方々が「現象学は最悪・凶悪である」と不平をこぼすのは、自己診断とは違う仕方で外部からコンピュータの動きを探ろうとしてツールをインストールしようとすると、セキュリティ保護プログラムがいちいち警告を出してウザい、と文句を言うのに似ているかもしれない。「セキュリティプログラムを外してくれないと仕事にならないのに、現象学は一度入れるとアンインストールできない。OSをまっさらな状態で入れ直すしかなくて面倒くさい」、みたいな……。
直観の「生き生きした現前」は、外から観察すると、エンドユーザが難しいことを考えずにコンピュータを快適に利用している状態を連想させる。そして現象学という自己診断プログラムを走らせることができるためには、ハイスペックなマシンでメモリやCPUに余裕がなければ、たぶん無理だ。
(非力なマシンだと、自己診断プログラムを走らせたことで反応が「遅く/重く」なって日常業務に支障を来し、本末転倒ですもんね。)
余裕で自己診断プログラムをアップデートし続けるフッサールという人は、どれだけハイスペックだったのか。
ハイスペックマシンが稼働していると、「男の子」はそれだけで嬉しくなっちゃったりしますよね。
現象学に人が群がるのは、そういうところがあるのでしょう。
研究室で3Dシミュレーションをリアルタイムにグリグリ動かすフッサール。(プログラムを書き換えて、世界征服を企てるその助手ハイデガー。)
贅沢な中間者。
高度に幸福ではあるけれど、外部の侵入を拒絶する「心のgated community」になる危険が絶えずつきまとう。