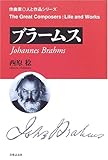[追記あり]
第1曲がパレストリーナ様式のア・カペラ合唱を顕彰して、第2曲の前半が雄弁なオーケストラに支えられたバッハのコラール・カンタータ風で、後半はヘンデルのオラトリオやその影響を受けた古典派(「第九」を含む)を思わせるドラマ仕立ての合唱。第3曲は、ロマン派のドイツ語オペラの取り組みの成果を踏まえたと思われる朗唱からフーガ(=音楽における普遍言語)へ。
「大文字の音楽史」のパースペクティヴをそのまま作品化したような前半(作曲者は1867年に一旦ここまでの部分を試演している)を調べながら、
ドイツ(ルター)が他に先駆けて聖書を母国語に訳して、母国語による礼拝を敢行したことは、音楽におけるナショナリズムと事後的にしかつながらないものなのか、知りたいと思った。(イングランドにも英国教会のサーヴィスがあるけれど。)
同じ地域の同じ時代、あるいはひとりの作曲家であっても、ラテン語などの国際的に通用する言語のテクストへの作曲と母国語への作曲ではスタイルが違うことは珍しくないのだから、「音楽におけるお国柄」問題は、声楽を視野に入れると一段と複雑になる。
そしてブラームスのドイツ・レクイエムは、ドイツ流の「趣味の混合/混合趣味」を過去に遡って集大成するようなところがあるわけだけれど、そのすべての様式を「ドイツ語で」歌う。そしてこういう形の典礼を教会で行う前提で書いたわけではないコンサートホールの音楽で、歌詞選びもブラームス自身が行っている……。
(そういえば、オペラにおいてワーグナーが自分で台本を書き、ヴェルディが台本作家に細かく注文を出したのは作曲家の地位の変化を示すと説明されるが、保守的と言われるブラームスが自分の意志でテクストを編んだことは、宗教音楽の歴史のなかでどの程度新しいことだったのか。
あと、カンタータを書いてコンクールに応募するパリのローマ賞みたいな明白な新人の登竜門のないドイツで、この作品がブラームスの「出世作」とされるのは、誰がどういう脈絡で彼の「出世」を認定しているのだろうか。)
言語と宗教が絡み、ドイツの音楽におけるナショナリズムの色々ややこししところを突く作品のような気がするのだけれど、こういうのは、学問制度上、「言説史」の素材からは外れるのかしら。だったら、こういう案件は何学で扱えばいいのか?
あるいは昭和の作曲家で仏教洋楽や式典音楽を書くときにドイツ・レクイエムのことを考えた人はいなかったのだろうか。
(そもそも日本初演はいつ誰がやって、オーケストラや合唱団ではどれくらいの位置づけの曲なのでしょうか。「近代化」と「西洋化」を同時進行で受容したときに、「西洋器楽」のように言葉と切り離して「音(楽)」を洗練させるのが「近代的」だ、と思える局面があったかもしれず、ワーグナーはそのような予見のフィルターを通したときに過剰に素晴らしく思えるタイプの音楽劇で、ブラームスのドイツ・レクイエムは、彼のキャリアにとっては重要なのに、シンフォニーと違って扱い難い位置に押しやられてしまった、とか、そういうことはないのだろうか。)
なんだか、病院をたらい回しされたように行き場のない疑問と不満を残しつつ、仕事に戻ります。
これだけ前半で力を入れたのだから、最後は軽く流してくれたらいいのに、ドイツ・レクイエムは後半の2曲がまた長い……。モーツァルトのミサ曲みたいにソプラノのアリアで軽やかに終わりにしてくれてもいいのに(笑、モーツァルトは、ザルツブルクの典礼改革で長いミサがNGだったから曲を短くまとめざるを得なかったと見られているようですね、そういう外からの枠がないコンサート音楽は、ベートーヴェン以後どんどん長くなった……)。
[追記]
- 作者: 西原稔
- 出版社/メーカー: 音楽之友社
- 発売日: 2006/06/01
- メディア: 単行本
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
西原先生の評伝(あとがきを見たら、2006年刊行の本書の音楽之友社担当は木村元だったんですね)で、ドイツ・レクイエムの素材の出典は、貸し借りの帳簿を見るように疑問が氷解。
シュッツ以来のドイツ語典礼音楽の歴史は大事そうですね。
しかし、19世紀半ばにシューマンとかメンデルスゾーンとかワーグナーとか、市民階級出身の「意識の高い」ドイツ人音楽家が若くして国際的に活躍・交流した華やかな時代のあとなのに、街の楽師(Stadtpfeifer)の息子ヨハネス・ブラームスの前半生はめちゃくちゃ地味。ハンガリー系ユダヤ人脈(←「中東欧の回路」!)にアクセスして一歩また一歩と仕事の幅を広げる苦労の連続。中央集権の国家があって、学校というエスカレータが整備される前の、階級社会が露骨に残っていた時代は、ブラームスのように家業が音楽で手に職がある人でも、自分の属する階級の分際を外れて仕事の可能性を広げるのは一苦労だったようですね。
(ひょっとすると「2月以前」のドイツ人音楽家の活躍は、本人たちがロマン主義のポエジーの熱に浮かれるお目出度いインテリだったのと、パリやロンドンに外国人で新種の音楽ができる人材の需要があったのと、彼らがサロン社交界へアクセスできる身分だったことなどが複合した一種のバブル、火事場の活況だったかも。世紀後半に国民国家が編制されるようになって、世紀前半との表面上の音楽様式の違いはそれほど大きくないけれど、社会構造的には、みんな、ゼロベースで色々なことをやり直さなければいけなかった。ブラームスやブルックナーやフォーレのように、非主流から叩き上げた人が浮上してくるのは、社会の再編成の兆しと解釈したほうがいいかもしれませんね。そうこうするうちに、普仏戦争の賠償金でドイツが起業バブル(泡沫会社創業時代、と言われたりする本格的な産業革命の到来)になったりして……。多分「大文字の音楽史」なるものが構築されるのは、そうやって音楽家の頭数が揃って、色々な制度が整った頃からで、「クラシック音楽」なる文化が国際的に安定するのは、さらにあと、「ジャズ」と呼ばれた大衆音楽の台頭と、実はほぼ同時期ではないかと思う。)
そんな「国民国家以前」のドイツをちょっとのぞいただけでも、本気の自己責任社会は辛そうだし、日本が、今からそんな風にやっていけるとはとても思えない。
中国との関係もそうだし、中世から近世の東南アジアとの関係でも、この列島は、海を隔てて行きにくい辺境(東南アジアの交易圏の中のはじっこで、琉球とは全然条件が違う)なおかげで、おっとりやってこれたのだと思う。「国際情勢」の掛け声に乗せられると、地政学的な現実と乖離しそう。良くも悪くも、この列島は、外の危機が内部まで即座に浸透するほど薄くシンプルではない。時を稼いで様子を見る、は、決して悪い考えではないかもしれない。
- 作者: 村井章介
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2012/04
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
ポストコロニアリズムで日本を見直そう、の吉見俊哉先生は、鶴見良行を入口にして、日本と東南アジアを語る人になっていくんだろうか。
- 作者: 鶴見良行
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1995/11/20
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (22件) を見る