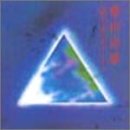[2/14、1955-57年の大栗裕の関西歌劇団創作歌劇公演関連3作品について、コメントを追加しました。]
[8/9:「飛鳥」に関連して1960年代のなにわ芸術祭について、8/10:関西歌劇団創作歌劇公演の当初の構想についての記述をそれぞれ補足しました。]
はびきの市民大学で昨年10月から今年の1月までやらせていただいた大栗裕講座(http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20091114/p1)。3回目にオペラの話をさせていただきまして、これが、講座前半では一番大事な回だったように思っています。
ただ、受講生の皆さんに相当な予備知識が要るテーマですし、大栗裕のオペラ/音楽劇については、調べれば調べるほど話が広がり、とても全貌が見えてはいない状態で、講座は、日本のオペラ史を(團伊玖磨「夕鶴」あたりまで)概説して、大栗裕のデビュー作「赤い陣羽織」(1955)をご紹介したところで終わってしまいました。(「アカジン」が面白い出し物で、当時、関西がオペラで頑張っていたことはご理解いただけたようなので、ほっとしていますが。)
- 作者: 増井敬二,昭和音楽大学オペラ研究所
- 出版社/メーカー: 水曜社
- 発売日: 2003/12/25
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
12回の講座全体を通しても、大栗裕のオペラについては、他に第2作「夫婦善哉」(1957)と、最後のオペラ「ポセイドン仮面祭」(1974)のごく一部分をご紹介するだけしかできませんでした。
改めて、大栗裕のオペラについて、そもそも彼はオペラをいくつ書いたのか? とりわけ1960年代前半、具体的には「夫婦善哉」のあと、「飛鳥」(1967)を発表するまでの、既存文献ではゴチャゴチャしてわかりにくい十年間の事情について、まとめてみようと思います。
-
-
- -
-
大栗裕のオペラは全部で7つあります。そして関西歌劇団の動向と連動させながら、3つの時期に分けて考えではどうかと思います。
- (1) 武智オペラの時代(1955-1957):「赤い陣羽織」(1955)、「夫婦善哉」(1957)
- (2) 創作オペラ空白期(1958-1966):「雉っ子物語」(1958)、「おに」(1960)
- (3) 創作オペラのイベント化(1967-1974):「飛鳥」(1967)、「地獄変」(1968)、「ポセイドン仮面祭」(1974)
●武智オペラの時代(1955-1957)
「武智オペラ」は、「歌舞伎演出の再検討」を掲げた昭和20年代半ばから後半にかけての武智鉄二演出による関西実験劇場の若手歌舞伎公演が「武智歌舞伎」と通商されているのをもじった私の造語です。(実際に「武智オペラ」という言葉が当時のジャーナリズムで使われた例もあるようですし。)
- 作者: 権藤芳一
- 出版社/メーカー: 和泉書院
- 発売日: 2005/07
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
関西歌劇団での武智鉄二の仕事について、結論だけをまとめますと、
朝比奈隆によって関西歌劇団に招かれた武智鉄二の提唱ではじまった創作歌劇公演は、当初の予定では、一幕もの小編成オペラ(当初「オペラ・プティ」と通称されていた)を1955年からの2年間4公演で合計8作一挙にやる構想でした。
実際の公演は、以下の通り。
- 創作歌劇第1回公演 1955年6月・三越劇場 「白狐の湯」*初演(原作:谷崎潤一郎、作曲:芝祐久)、「赤い陣羽織」*初演(原作:木下順二、作曲:大栗裕)
- アーティスト: 朝比奈隆,大栗裕,大阪フィルハーモニー交響楽団
- 出版社/メーカー: EMIミュージック・ジャパン
- 発売日: 2002/03/27
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (3件) を見る
- 創作歌劇第2回公演 1956年3月・産経会館 「マンドリンを弾く男」(原作:谷崎潤一郎、作曲:芝祐久) 「卒塔婆小町」*初演(原作:三島由紀夫、作曲:石桁眞禮生)
芝祐久 作品全集(13) 歌劇アリア曲集 (芝祐久作品全集)
- 作者: 芝祐久
- 出版社/メーカー: 音楽之友社
- 発売日: 2004/02/13
- メディア: 楽譜
- この商品を含むブログ (1件) を見る
石桁真礼生 歌劇「卒塔婆小町」 (オペラ・ヴォーカル・スコア)
- 作者: 石桁真礼生,三島由紀夫
- 出版社/メーカー: 全音楽譜出版社
- 発売日: 1998/12/10
- メディア: 楽譜
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- 創作歌劇第3回公演 1957年3月・産経会館 「夫婦善哉」*初演(原作:織田作之助、台本:中沢昭二、作曲:大栗裕)
- 創作歌劇第4回公演 1957年11月・三越劇場 交響的物語「杜子春」*初演(原作:芥川龍之介、構成:武智鉄二、作曲:大栗裕) 「羽」*初演(原作:小泉八雲、台本:中沢昭二、作曲:田中正史)
武智鉄二は、当時、多方面の活躍でマスコミの寵児もしくは風雲児でした。色々な騒動でもみくちゃになりますが、3年かかったとはいえ、ちゃんと予定通り4公演をやりとげ、7本を制作しました。「マンドリン」以外すべて初演ですから、大変なエネルギーの要る仕事だったろうと思います。
武智鉄二がのちに「青春だった」と振り返り、朝比奈さんは初対面の中丸美繪さんに「武智という男がいてね」とホテルのバーで楽しそうに語り始めたそうですが、相当に熱い時代だったのでしょう。(中丸さんはあまり書いてくれませんでしたけれど……)。
原作との関係に着目するだけでも、
(a) 原作戯曲にそのまま作曲する文学オペラ(「白狐」、「赤陣」、「マンドリン」)。
- 作者: 谷崎潤一郎,千葉俊二
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 1999/08/18
- メディア: 文庫
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
(b) 原作を作曲者が再構成して作曲(「卒塔婆小町」)。
- 作者: 三島由紀夫
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1968/03/27
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 35回
- この商品を含むブログ (76件) を見る
(c) オペラ台本を作成しての作曲(「夫婦善哉」、「羽」)。
- 作者: 織田作之助,種村季弘
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1999/05/10
- メディア: 文庫
- クリック: 27回
- この商品を含むブログ (27件) を見る
- 作者: 小泉八雲,森亮
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 1988/06
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る
(d) 朗読と管弦楽による語り物形式(「杜子春」、語り手は茂山千之丞さんでした)。
- 作者: 芥川龍之介
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1968/11/19
- メディア: 文庫
- 購入: 5人 クリック: 67回
- この商品を含むブログ (131件) を見る
……というようにバラエティに富んでいます。
「夫婦善哉」は一晩ものに膨れあがり、もはや「オペラ・プティ」と呼べない規模ですが(大阪言葉でしゃべり続けて「歌がない」という本作の特徴は、おそらく、試験的な一幕ものが予定外に規模拡大したことによるヒズミ・見込み違いでしょう)、一晩ものが一つ入ったことでラインナップが多彩になり、歌劇の色々な可能性をデモンストレーションする結果になりました。
谷崎、三島といった原作の選択から美術・演技指導・舞踊振付などまで武智イズムに貫かれたシリーズです。
(谷崎潤一郎や三島由紀夫は、稽古や本番にも立ち会いました。)
谷崎潤一郎詳細年譜 http://homepage2.nifty.com/akoyano/tanizaki.html
- 作者: 小谷野敦
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2006/06
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 31回
- この商品を含むブログ (35件) を見る
大栗裕は、このシリーズで作曲家デビューしました。しかも創作歌劇シリーズ全7作品のうち約半数の3作品が大栗裕の作品です。
[2010/8/10補足]
ただし、結果的に大栗裕の作品が多くなりましたが、武智鉄二は当初、はばひろく日本の作曲家たちにも参加を呼びかけてたようです。第1回公演プログラムによると、
私は多くの作曲家にあって、民族歌劇創造のための協力を依頼した。私の最もうれしかったことに、その総ての作曲家が協力を約束してくれた。松平頼則、清瀬保二、清水脩、団伊玖磨、黛敏郎、芥川也寸志、石桁真礼生、湯浅穣二の諸氏である。(全文はhttp://www3.osk.3web.ne.jp/~tsiraisi/musicology/article/ohguri-hiroshi20080415.html)
これだけの作曲家に声をかけていたようです。
朝比奈隆にも、新しい「日本の」演劇創造という自負があったようです。第1回公演プログラムには「日本の言葉、日本の脚本、日本の音楽……」などの言いまわしがあり、「私はシンフォニーは国際的なものだけれども、オペラは民族と結びついたものだと思っています」(『音楽藝術』1958年2月号147頁)とのちに語っています。(関西・大阪の音楽事業で「日本の」という言葉を使うのは、現在の感覚だと大げさで違和感を抱く方が少なくないと思いますが、1950年代にはじまった在阪民放放送局にも同様の発想が見られます。当時はまだ現在ほど東京一極集中が進んではいなかった、少なくとも当時の関西文化のリーダーたちは今日のように極端な東京集中の状況になるとは思っていなかったのかもしれません。)
終わってみれば、関東在住の作曲家で作品を提供したのは芝祐久と石桁真礼生の二人だけでした。
大言壮語と竜頭蛇尾を揶揄することは簡単ですし、作曲家たちを本気にさせる何かが足りなかったのかもしれませんし、武智鉄二の派手な動きは、スキャンダラスな情報ばかりが面白おかしく伝えられて東京の人たちをかえって警戒させてしまうところがあったのかもしれません。
日本の再独立直後に沸き起こった創作オペラ・ブームに浮き足だったところがあったのは否定できず、計画倒れに終わった企画が二期会と大阪労音の共同制作など、他にもあります。
でも方針変更などのやりくりを余儀なくされつつ、死屍累々と言えるかもしれない騒動のなかで、それでもこれだけのことをやった、という結果は評価されるべきでしょうし、関西の関係者が主になったとはいえ、「新しい日本の」という形容が不当とは言い切れないヴィジョンや提言は十分に含まれているのではないか。
「所詮あれは関西ローカルの試みであった」とする矮小化や、そのような判断の前提になっている基準のほうを再検討することがあっていいのではないか、というのが私の考えです。(参考:http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20101028/p1)
[補足おわり]
[ここから2/14加筆・追記]
「赤い陣羽織」は、武智の演技プランにあわせて音を付けたと言われています。
「夫婦善哉」では、船場育ちの大栗裕に、河内弁とは違う大阪の商家の言葉(いわゆる「船場言葉」)のイントネーションで作曲させるのが、自身も商家出身で泥臭い河内文化が好みではなかった武智鉄二の狙いだったようです。
「杜子春」は、いわゆる音楽物語です。衣装や所作を伴わず、歌劇に分類することはできないと思いますが、日本の演劇が語り物という水脈で育ったことを踏まえて、「新しい国民劇」を目指す創作歌劇運動に、現代の語り物として音楽物語を導入したのだと思われます。
[ここまで2/14加筆・追記]
大栗裕の作曲家としてのキャリアは「武智チルドレン」としてスタートしたわけです。
-
-
- -
-
なお、1954年11月の「修禅寺物語」(原作:岡本綺堂、作曲:清水脩)は、武智鉄二の演出ですが、上記創作歌劇シリーズ立ち上げ以前の公演で、関西歌劇団が公開している過去の上演リストでは、「特別公演」の扱いになっています。
それから、武智鉄二は一時期、関西歌劇団で「顧問」の肩書きも得ていたらしく、1954年の「お蝶夫人」と「修禅寺」が当たったあと、1955年から1956年前半には、「パリアッチ」、「カルメン」、「魔笛」などの“赤毛もの”も手がけました。
(今ではモーツァルトはオペラの作曲家として認知され、学生が上演したりします。ワーグナーやリヒァルト・シュトラウスとあわせて、ドイツこそがオペラの本場だと思いこんでいる方もいらっしゃるようで……。「ドイツは交響楽の本場、楽聖ベートーヴェン」等といった教養主義の賞味期限が切れてしまったので、ドイツ好き男子がオペラの分野でのお家再興を画策しているのでしょうか……。
でも、当然ながら日本でも、戦前までオペラといえば、オペレッタと「カルメン」以外は、ほとんどがイタリアものでした。「フィガロの結婚」を1952年に芸術祭主催公演で日本初演したのは、当時のオペラ界の一大イベント。「魔笛」の日本初演は翌1953年。モーツァルトのオペラは、ごちゃごちゃして上演が面倒な特殊なものだったと見たほうがよさそうです。
武智演出による関西歌劇団の「魔笛」は、モーツァルト生誕200年にちなんだ上演で、このとき、日本初演からまだ3年しか経っていません。そういえば、ちょうどこの1956年創立の京都市交響楽団は、小編成を生かしてモーツァルトで評価を高めたそうです。大フィルとの差別化が上手くいったのですね。京都はモーツァルトと相性がいいのでしょうか……。)
- 作者: 岡田暁生
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2008/03
- メディア: 単行本
- 購入: 3人 クリック: 28回
- この商品を含むブログ (19件) を見る
武智鉄二がこうした洋物に手を出したことは、当時、関西の音楽評論家から総攻撃を浴びました。1956年後半から、武智鉄二の関西歌劇団への登場は、創作歌劇公演だけになります。
(評論家による武智批判は、武智がすぐさま反論して大騒ぎになるのですが、評論家の言い分は不当だったのか、歌舞伎の人がオペラの縄張りへ侵犯することへのセコい反発だったのか、それとも、これらの演目では新作ほど練習期間を取れなかったらしいので、実際に不備のある公演だったのか。武智鉄二の活動を「オペラにおける演出家の時代」の先駆と再評価可能かどうか。今後、さらに調査が必要だと思っております。)
●創作オペラ空白期(1958-1966)
実際には細々とオペラが作られてはいたので、「空白期」は言い過ぎとは思いますが、上記「創作歌劇」全4回が終了してから、関西歌劇団は新作の制作を約10年間やっていません。
武智鉄二は、家業が傾いて(ただし、いくらカネがかかると言っても、当時世評で言われたように武智が芝居に私財を注ぎ込んだ末の破産、ではなさそうですが)、関西の家をたたんで、東京へ移住。のちに小説家デビューするも盗作疑惑で消えた西村みゆきとの同棲を経て、1959年に日本舞踊の川口秀子と結婚します。
- 作者: 栗原裕一郎
- 出版社/メーカー: 新曜社
- 発売日: 2008/07/01
- メディア: 単行本
- 購入: 12人 クリック: 428回
- この商品を含むブログ (106件) を見る
武智がオペラ演出を再開するのは、1960年代の映画監督時代を経て、
- 出版社/メーカー: 彩プロ
- 発売日: 2007/12/21
- メディア: DVD
- クリック: 43回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
- 出版社/メーカー: 彩プロ
- 発売日: 2007/12/21
- メディア: DVD
- クリック: 19回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
1970年代に、日本オペラ協会と関わりはじめてからです。
- 作者: Minoru Miki
- 出版社/メーカー: 全音楽譜出版社
- 発売日: 1998/12/10
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- 作者: 三木稔
- 出版社/メーカー: 中央アート出版社
- 発売日: 2001/09/22
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
(一方、関西歌劇団の演出は、劇団長の朝比奈隆自身がやったり、茂山千之丞さんに頼んだり、あるいは、宝塚歌劇から演出家を迎えます。)
- 作者: 茂山千之丞
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1987/12/21
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 1人 クリック: 18回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
- 作者: 谷崎潤一郎
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2005/11/25
- メディア: 文庫
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
1958年6月に「さるかに合戦」(作曲:近藤圭)、同年7月に「雉っ子物語」(台本:中沢昭二、作曲:大栗裕)の公演がありますが、これは、兵庫国際会館における「小中学生のためのオペラ」という位置づけでした。(初演プログラム等の資料が乏しく、詳細はよくわかりません。)関西歌劇団の上演リストでは、この2公演は「特別公演」に分類されています。
「雉っ子物語」は、実は前年にJOBKで放送されたラジオ・ミュージカルス「牛方とど」を一部改訂して舞台上演したものです。
また、関西歌劇団第19回定期公演(1965年5月)では、「おに」(台本:中沢昭二、作曲:大栗裕)がストラヴィンスキー「エディプス王」(日本初演)と二本立て上演されますが、これは、5年前1960年の作曲、京都女子学園創立50周年記念公演委嘱作品の再演です。
創作歌劇シリーズは経費がかさんだことでしょうし、1960年代前半には、放送局や祝賀イベントなど、特別な出資者がいなければ新作を作ることができない状態だったのかもしれません。関西歌劇団は、低予算でやりくりできる演目を模索していたように見えます。
[補足2010/8/9]
その後いくつか資料を整理してみると、1960年代前半は、創作歌劇だけでなく、オペラ公演そのものが大変だったようです。
関西歌劇団は、1961〜65年は定期公演自体が年一回にペースダウンしています。
また1964年の第18回定期公演(「カヴァレリア・ルスティカーナ」と「赤い陣羽織」)は、この年からはじまったサンケイ新聞社主催なにわ芸術祭に組み込まれています。
1965年の第19回定期公演(「エディプス王」と「おに」)が同第2回、1966年の第20回定期公演(「コジ・ファン・トゥッテ」と関オペ久々の新作となる近藤圭「賤のおだまき」)は同第3回、1967年の第22回定期公演(大栗裕「飛鳥」)は同第4回。会場はいずれもサンケイホール。
大栗裕の最初の本格グランド・オペラ「飛鳥」は、この時期にサンケイホールと関西歌劇団の協力関係があったがゆえに実現した作品ということになりそうです。
(そして「飛鳥」を制作したあと、なにわ芸術祭がオペラ公演を打つことはなくなります。関西歌劇団は、コンサート形式のガラやハイライトでの出演になっています。)
[補足おわり]
-
-
- -
-
しかも、1960年頃の音楽雑誌をみると、50年代にはオペラの自主制作を目指すほど盛り上がっていた大阪労音がオペラに見切りをつけて、ミュージカルに乗り換え、ペギー葉山などを起用した新作で注目を集めます。(例えば、黛敏郎作曲「可愛い女」。)
またオペラ興行としては、NHKが電波を通して全国津々浦々にオペラを広めたイタリア歌劇団や、大阪国際フェスティバルによる海外歌劇場招聘事業がありました。「本場」の舞台がどういうものか日本にいながらわかる時代になって、幸か不幸か、「追いつき追い越す」べき新たな目標をオペラ界は発見してしまいます。
(音楽取調係以来、日本の洋楽関係者には、西洋をお手本にして努力するときに「燃える/萌える」というDNAが仕込まれているのかも。その後しばらく落ち着いたと思ったら、最近は、いわゆる「読み替え演出」で、またもや「追いつき追い越せ」を嬉々としてやっていますし……。しかも「読み替え」大好き派は、同時に、前述のモーツァルト/ワーグナーのオペラを持ち上げてドイツ帝国再興を待望する派閥でもあり、リクツがお好きらしいので、さらに話がややこしいですね。)
- アーティスト: トゥッチ(ガブリエルラ),シミオナート(ジュリエッタ),デル・モナコ(マリオ)
- 出版社/メーカー: キングレコード
- 発売日: 2002/10/02
- メディア: DVD
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
- 作者: 畑中良輔
- 出版社/メーカー: 音楽之友社
- 発売日: 2009/09/16
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- 作者: 許光俊
- 出版社/メーカー: 青弓社
- 発売日: 2006/05
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 57回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
こうした世間の動向を見ると、1960年代に関西歌劇団が新作に取り組まなかったのは、1950年代にビュービューと吹き荒れていた創作オペラへの「追い風」が、パタリと止まってしまったせいでもあるようです。
その上、1960年には「暗い鏡」(のちに「ヒロシマのオルフェ」と改題、台本:大江健三郎、作曲:芥川也寸志)が出てきて、オペラも前衛派に領有されそうな気配。大栗裕の立場はなかなか微妙です。
- アーティスト: 本名徹次&オペラハウス管弦楽団
- 出版社/メーカー: (株)カメラータ・トウキョウ
- 発売日: 2002/11/20
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (1件) を見る
-
-
- -
-
1960年代前半、関西歌劇団が新作上演をできなかった時期に、大栗裕は音楽物語でしのいでいた、と見ることができそうです。(大栗裕の音楽劇をトータルに論じようとすると、この時期の音楽物語の経験が、関西歌劇団のオペラ創作が再始動したときに生かされたかどうかが、ひとつのチェックポイントになるだろうと思います。)
大栗裕は、1958年から技術顧問をしていた関西学院マンドリン・クラブで、1961年6月にソプラノとマンドリン・オーケストラのための「マーヤーの結婚」を初演。翌1962年6月には、ソプラノ、バリトン、合唱とマンドリン・オーケストラという大掛かりな編成で「ごん狐」を初演します。
- 作者: ハンス・クリスチャンアンデルセン,イブ・スパングオルセン,Hans Christian Andersen,Ib Spang Olsen,大塚勇三
- 出版社/メーカー: 福音館書店
- 発売日: 2003/11/20
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
- 作者: 新美南吉,黒井健
- 出版社/メーカー: 偕成社
- 発売日: 1986/10/01
- メディア: ハードカバー
- 購入: 2人 クリック: 56回
- この商品を含むブログ (67件) を見る
この2つの作品は、同クラブの初夏の演奏会(現在のイブニング・コンサート)での上演ですが、1964年には、ソプラノとマンドリン・オーケストラのための「星」を11月の定期演奏会で発表。
- 作者: 桜田佐,Alphonse Daudet,ドーデー
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1958/01
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
以来、1970年代にかけて、ほとんど毎年のように、マンドリン・オーケストラのための音楽物語を作っています。当初はもっぱら関学用、のちには京女や他の大学からも依頼が来ます。
なお、大栗裕の一連のマンドリン・オーケストラ作品は、曲ごとに「ミュージカル・ファンタジー」、「童謡オペレッタ」など色々な副題がついていますが、いずれも扮装や所作なしで、語り手が進行役になる音楽物語として初演されたようです。
けれども一方で、先にご紹介したように、語りと管弦楽による音楽物語「杜子春」を関西歌劇団が創作歌劇公演の枠で初演した例があり、同作は1960年の京女50周年公演では、茂山千之丞さん演出で、所作を伴うオペラとして再演されました。マンドリン・オーケストラのための音楽物語のなかにも、宝塚歌劇団メンバーによるテレビ放送劇にリメイクされたり、影絵を伴う形、衣装と所作つきのオペラ形式での再演が確認されております。
ちょうど「兵士の物語」や「火刑台上のジャンヌ・ダルク」の上演形態に幅があるように、大栗裕の場合も、オペラと音楽物語、放送劇の境目は流動的です。
火刑台上のジャンヌ・ダルク*オペラ・オラ [Laser Disc]
- 出版社/メーカー: ファンハウス
- 発売日: 1994/08/25
- メディア: Laser Disc
- この商品を含むブログ (1件) を見る
●創作オペラのイベント化(1967-1974)
最後の第三期、「飛鳥」以後の3作品については、関西歌劇団の定期公演で初演されており、上演記録や公演評などで概要を簡単に確認できるので、あまり詳しくまとめなくてもいいだろうと思います。
「飛鳥」は、上でもそこに至る経緯をご紹介しましたが、1967年5月に、なにわ芸術祭(産経新聞主催)の一環として初演されて、同年9月には民音主催で再演されました。原作は太宰治の「走れメロス」。舞台を上代の奈良に置き換えて、宝塚歌劇団の演出家、菅沼潤の脚色と演出です。(身替わりが友人ではなく、恋人の女性に変更されており、イジイジしない主人公像は、太宰作品よりも、翻案元のシラー「人質」に近いですが。http://de.wikipedia.org/wiki/Die_B%C3%BCrgschaft)
- 作者: 太宰治
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2005/02
- メディア: 文庫
- 購入: 7人 クリック: 124回
- この商品を含むブログ (177件) を見る
(菅沼潤さんは、「モン・パリ」や「パリゼット」の白井鐵造の弟子筋に当たる人で、本作以後、大栗裕とコンビを組むことになります。
- 作者: 渡辺裕
- 出版社/メーカー: 新書館
- 発売日: 1999/10/28
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (7件) を見る
「夫婦善哉」以来、60年頃まで大栗裕と組んでいた中沢昭二は東京へ移って放送作家の仕事を続けて、その後、小説家に転身します。1974年のNHK大河ドラマ「勝海舟」で倉本聰降板後の脚本を担当した人です。)
- 作者: 中沢昭二
- 出版社/メーカー: 八広社
- 発売日: 1982/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
「地獄変」は、翌1968年10月初演。原作は芥川龍之介。脚色・演出は菅沼潤。1970年7月には、万博クラシック公演として茂山千之丞さんの演出で再演されました。
- 作者: 芥川龍之介
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1968/11/19
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 30回
- この商品を含むブログ (53件) を見る
そして「ポセイドン仮面祭」は、1974年11月、関西歌劇団創立25周年記念公演。原作、辻邦生。脚色と演出、菅沼潤。大変面白い出し物だと私は思うのですが、関西歌劇団総出演の大掛かりな演目で、再演は一度もありません。(なにか、良い上演機会はないものでしょうか?)
ポセイドン仮面祭―祝典喜劇 (1973年) (書下ろし新潮劇場)
- 作者: 辻邦生
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1973
- メディア: ?
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
この3作品は、既にヴァイオリン協奏曲などを書いたあとの大栗裕のシリアスな代表作。「飛鳥」ではサンケイ・民音とタイアップ、「地獄変」は万博の舞台に乗り、「ポセイドン」は関西歌劇団の記念公演ですから、以前に書いた、野口幸助流のプロデュースが力を発揮した企画とも言えそうです。
http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20100127/p1
……こうして眺めてみると、オペラ作曲家としての大栗裕のキャリアはなかなか立派。「いざやってみると大変で、二度とオペラは書くものかと思う」とコメントを残しましたが、やはりこの人は劇音楽の作曲家だなあ、と思います。
それから、今回こうして原作へのリンクを貼ってみると、誰もがおよその話を知っている物語が選ばれていますね。「ヴォツェック」とか「ねじの回転」などもあるべきでしょうけれど、長く愛されることを目指すとしたら、難しくて立派なだけではオペラには向かないということでしょうか。
洋物オペラだと、原作の文学としての格、高級度や大衆度がよくわからなかったりしますが、こうして日本の文学が原作だと、台本選択のニュアンスまで、素通しで見えてしまいますね。
-
-
- -
-
世に流布している戦後音楽史では、1950年代からの前衛音楽運動こそが作曲のメインストリームとされますが、オペラの動静をみると、60年代の騒ぎは一過性に過ぎなかったかのようにも思えてしまいます。「やめてけれゲバゲバ」と呪文を唱えていたら嵐が過ぎ去って、出資者を募るオペラ・イベントを次々実現できる楽しい時代が戻ってきたわけです。
そして前衛運動が生んだスター、武満徹は結局オペラを書くことができませんでした。晩年の彼のオペラ構想を周囲はあまり上手くいくと思っていなかったようでもあります。
とはいえ、大栗裕や関西歌劇団にとっては、1970年代のオペラ復興がめでたいハッピーエンドだったにしても、それじゃあ大栗裕が長生きして80年代バブルを迎えていたらどうなったか。
例えばさらに年上の柴田南雄のシアター・ピースが妙に成功して評価を得たりしたことを意識して、ひょっとすると、五線譜を離れた手法にも手を染めることになったのでしょうか?
大栗裕の自筆譜は、軍楽隊譲りに端正で実用的で、発想標語などはもちろん楽器名や演奏法まで、原則、全部イタリア語で統一されたオーソドックスなスタイルです。彼は、60年代にも決して図形楽譜などには手を染めなかったのですが……。
[参考:大栗裕のオペラについては、さらにこういう記事も書いています。http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20101028/p1。他に、大栗裕の歌劇・声楽の節付けの特徴についての考察http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20101109/p1と、関西歌劇団での配役についての考察http://d.hatena.ne.jp/tsiraisi/20101103/p1。 ]
(そして最後に一言。
大幅に話は逸れますが、1970年代後半から柴田南雄の評価が急上昇したのはなんとも奇妙だと思い、最近、気になっているのです。
一連のシアター・ピース絶賛で、遡って、柴田さんは1950年代のバルトーク紹介やレイボビッツで十二音をやった頃から常に先見の明があったとされ、還暦の1976年には、武満徹も「ミュージック・トゥデイ」で特集演奏会をやり、「音楽芸術」で大きな特集が組まれました。1980年代、ちょうど私が音楽学の学生だった頃には、音楽学者風に大きな企画の監修者に名前を連ねていらっしゃって、音楽学、とりわけ民族音楽学の大恩人と処遇されていました。(ご本人の姿も、1990年の大阪の音楽学会国際シンポジウムのときに拝見しましたが……。)
確かに、吉田秀和さんと双璧に上品・高学歴でお行儀の良い方だったみたいですし、民族音楽学の方々が彼の主張を有り難がるのは理解できるけれども、あんな風に「ゆく河の流れ」を総括されて、前衛の戦士の皆様は本当に納得したのでしょうか。あれではまるで、ルイ・シュポアの保守派丸出しな「歴史的交響曲」が正史に認定されたかのようですし、あれをメタ・ミュージックなどと仰々しく言ってしまっていいのか、と思うのですけれど。
- アーティスト: Spohr,Walter,Cssr State Philharmonic
- 出版社/メーカー: Marco Polo
- 発売日: 1994/07/19
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (1件) を見る
前衛の60年代が所詮その程度の総括で決着してしまうことなのだとしたら、前衛に賭けて晩年はかなり辛い立場になった松下眞一のような当事者だけでなく、前衛の嵐のせいで回り道することになった大栗裕も浮かばれないのでは、と思うのですが……。
頭を低くして第二次世界大戦を生き延びた大正生まれのインテリさんが、昭和生まれの若手による戦後の経済・文化闘争を生き延びて、結局、一番の栄光を得た。やっぱり頭のいい人が得をする、踊らされたのは阿呆であった、という話なのか?
学者として高等遊民的に生きていこうとする人にとっては、柴田南雄や吉田秀和の生き方が一つの理想かもしれず、彼らの歴史観の中でこうした人たちが良いポジションを占めてしまうのは仕方がないのかもしれませんが……。クラシック音楽はブルジョワ・知識人層のものだということで。)
- 作者: 柴田南雄
- 出版社/メーカー: 青土社
- 発売日: 1994/07
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- アーティスト: 柴田南雄,東京混声合唱団,ひばり児童合唱団,法政大学アリオンコール,お茶の水女子大学合唱団,合唱団「あらかわ」,おたまじゃくしの会,日本石油合唱団,酒井義長,田中信昭,関一郎
- 出版社/メーカー: ビクターエンタテインメント
- 発売日: 1996/05/22
- メディア: CD
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
- アーティスト: 東京都交響楽団,伊藤叔,東京混声合唱団,柴田南雄,若杉弘
- 出版社/メーカー: フォンテック
- 発売日: 1992/10/25
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (1件) を見る













![白日夢(64年) [DVD] 白日夢(64年) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51EZeNmggqL._SL160_.jpg)
![黒い雪 [DVD] 黒い雪 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AfzK8QNLL._SL160_.jpg)




![アイーダ*歌劇 [DVD] アイーダ*歌劇 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YC6HCBW1L._SL160_.jpg)